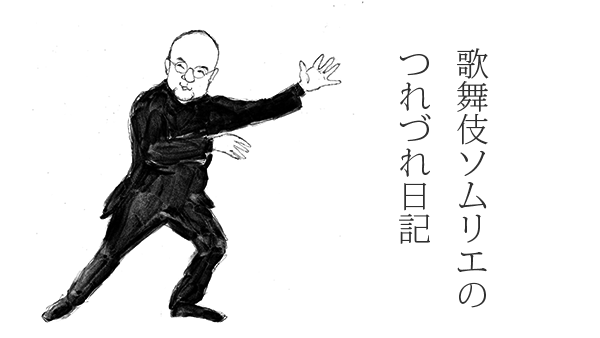輪島 追想その2
現役晩年の輪島は、けんか四つの対戦相手のときは、自分からあえて相手の四つに組んでいく、という取り口をしばしばみせた。
この相撲っぷりに、独特の味わいがあった。自分のほうの地力が明らかに勝っているときにそれは限られたわけだが、じっくりと相手の立ち合いを受けとめ、目一杯攻めさせながらだんだん相手の力を自分のなかに吸収、吸引するように消していき、満を持して投げなり寄りなり、しとめる。勝ち名乗りを受けるときには、あの印象深い猫背といかり肩で伏し目がちに行司の軍配を見つめ、淡々と手刀を切っていた。
横綱ゆえの余裕ともちがうし、風格ともちがう。相手得意の型、というリスクをあえておかしているんだ自分は、、という慎重さ、緊張感も、かなりあからさまに伝わってくるんだけど、次第次第に相撲内容は輪島のペースになっていき、落ち着くべきところに落ち着く、、、そういうなんともいえぬ流れが、見ていてスリリングで楽しかったし、趣きがあった。
昭和48年名古屋場所、輪島の新横綱の初日を、祖父と一緒に、ぼくは砂かぶりで見ている。大関に置き去られた貴ノ花はなかなか気運に乗れず、あの熱狂の大関同時昇進から一年足らずで、二人の明暗はあまりにも対照的だった。ぼくは目当ての貴ノ花の不調が悲しくて、土俵がすぐ真ん前だというのに、気持ちが盛り上がらない。
そんななかで輪島の、本場所で初めての土俵入りが始まったが、一番の見せ場のせりあがりで、輪島の腰が、ひょい、っと不恰好に持ち上がってしまって、場内がどっと沸いた。
と、輪島のからだじゅうが、みるみる、真っ赤になった。ああ、、、と祖父は気の毒そうな吐息をもらした。
輪島ざまぁみろ、とこころのなかで叫びかけてたぼくは、この身体中の色の変化に、祖父の吐息に、子供心になんだか、わけのわからないような申し訳なさ、恥ずかしさがこみ上げてきて、しばらく口が聞けなかった。