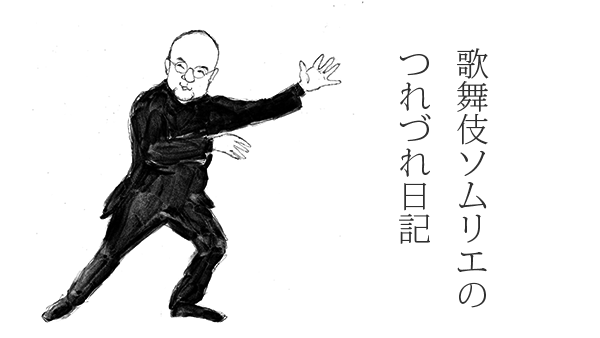Dec 17, 2018
12月の「阿古屋」を見て
12月歌舞伎座の話題は何といっても玉三郎、梅枝、児太郎の「阿古屋」だが、そのなかで、阿古屋が三味線を弾いている最中に、敵役の岩永がうとうとし始めるので、すぐ隣のさばき役・重忠が床を扇子で叩いてたしなめ、岩永があわてて目覚める、という場面がある。
しかし、ほんらいここでの重忠は、阿古屋が、離ればなれの恋人・景清のことを思いうかべ、こころ此処にあらずの状態になり、三味線を弾く手が止まってしまうので、それをたしなめ、また「さぁ、演奏を続けて」と助け舟を出すごとくにうながすために、扇子で床を叩いている、という芝居であるべきだろう。その叩く音が岩永の居眠りをおのずと起こすのである。
つまり、それくらい緊密な、真剣な気持ちのやりとり、こころの機微が、阿古屋と重忠のあいだには通っている。「縁なき輩」岩永ひとりがカヤの外に置かれているわけだ。こころをこめて三曲を奏でる阿古屋と、こころをこめて耳を傾け続ける重忠と、聞く耳をハナから持っていない岩永。主要人物三者がどんな関係かが、扇を叩く一瞬にあざやかに凝縮されている。
これを、扇子を叩いて岩永を起こしている、という解釈で演じてしまったら、根っこから意味が変わってしまうし、「阿古屋」という芝居の人間描写の深さが薄まり、作品の値打ちまで下がってしまう。そのことは、見ていて、はなはだ残念な気がした。
阿古屋という大役の後継者への伝承も大事だが、作品自体、作品全体の内容の解釈を、次の世代へ丁寧に受け渡しすることは、ある意味、もっと大切なはずだ。そこに落ち度があったのは、悔やまれる。画竜点睛とはここのことである。