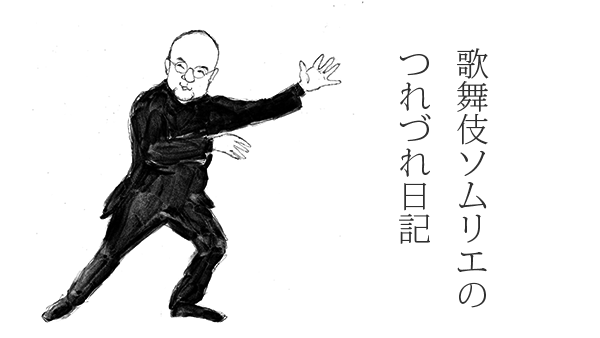句会
30代すぎから10年ちかく、句会に通ったことがある。いま振り返って、あれは本当にありがたかったなぁ、と思うのは、そのときの俳句の先生が、ごく普通の季語だけを毎回毎回、お題に出されたことだ。花、雪、月、梅雨、新緑、紅葉、枯れ木、、、毎年のように繰り返し繰り返し、オーソドックスな季語しかお題には指定しなかった。
たとえば花、雪、月であれば、いずれも二字・二音節だ。これを十七字のうちのどこにはめこみ、残り十五字をどう整えて、句としての語調やたたずまいを、きちっと整えるか。二字に慣れたら三字の紅葉や西瓜(すいか)、その次は四字の五月雨、木枯らし、さらに五字の鯉のぼり、初詣、山笑う、、、と、順をおって少しずつ学んでいくのである。
五字の季語になると、五・七・五のあたまの五か、おしりの五か、もしくは七のなかの五字を季語で埋めるか、の三択になるわけで、つまり、そういう言葉の整理整頓がいかに大切かを、先生は念入りに叩きこんでくださった。これをしないと、いつまでたっても、俳句のようなもの、なんちゃって俳句、を読み続けるはめになる。
たから逆にいえば、たとえば、さまざまな季語のバリエーションなどは、先生にとっては、二の次三の次だったわけだ。季語をたくさん知っていることや用いることと、いい句作り、、、技術のよしあしよりもむしろ、句作への臨みかたとしての「いい」とは、先生のなかでは全くの別物だった。ちゃんと使えもしない食材や調味料にあれこれ手を出したところで、ろくな料理は出来ないよ、とからから笑いながら指導してくださった。
お相撲の四股やてっぽう、ピアノの音階やアルペジオ、などなど、どの道にも、肝心かなめの基礎がある。俳句も同じだよ、ということをこの先生は、大切に大切に示してくださった。森よりも林、林よりも木。いかにありふれた普通の言葉で、ありふれていない感覚が伝わるか、その人ならではの味が出せるか、それが表現というものだ、とたびたび語ってらっしゃった。
何がいつの季語、という知識を嬉しそうにひけらかすような振る舞いや、やたらとそれを用いる句作りが、とにかく先生はきらいだった。だのに、俳句を歌舞伎に置き換えたとき、このての醜い振る舞いを、自分はいまだに、しょっちゅうしている。あのころ何を学んでいたんだおれは、と、その度にがく然とするのである。